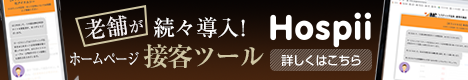さて、今回は塩釜のメインストリートへ。
鹽竈神社の参道入り口前に横に広がる商店街。

この商店街には享保9年(1724年)から続く宮城県を代表する酒蔵佐浦があったり、天明4年(1785年)に創業した老舗和菓子処おさんこ茶屋、明治8年創業の駄菓子屋さんやまだ屋、万延元年(1860年)創業の酒屋熊久商店、明治27年(1894年)創業の阿部平かまぼこ店、大正5年(1916年)創業の菊良紙店と、約300mくらいのあいだに多数の老舗が残っています。
そんな中、まだほかにも100年以上続く老舗があったんですね。
この佐浦の二軒隣にあるこちら、市川紙店です。

市川紙店は明治35年(1902年)創業の老舗文房具屋さん。
明治35年は骨牌税(こっぱいぜい)法が公布された年。
骨牌税とは戦後まで存在した日本の間接税の一つで麻雀牌や花札、トランプなどギャンブル性の高いカードゲーム類に課せられた税金です。
その後昭和32年にトランプ類税と変わりましたが平成元年の消費税導入に伴う間接税の整理で廃止されました。
そういえば昔のトランプって印紙みたいなの貼ってありましたよね、あれはその税金を納めたという証です。

お店の外観はそうでもないんですけど、看板の字が歴史を感じます。

仙台弁こけしグッズがあるんですね、これは気になりますね。
店内に入ると、町の文房具屋さんといった感じで筆記用具やノート、のし袋、おりがみなどいろいろなものが置かれています。

お店の外に飾られていた仙台弁こけしの手ぬぐいはありましたが、他にもあるのかな……。
お店の方に「仙台弁こけしグッズって他にありますか?」と聞くと、「結構売れっちゃってね~、ここにあるだけ」と手ぬぐい以外でいくつか残っている仙台弁こけしグッズを教えてくれました。
その中から一つ、いい感じのものを選び購入。
それがこちらです。

かわいい……、これ巾着なんです。
「んだ」。
仙台に住んでいると、若い人の言葉は標準語とあまり変わりはありませんが、年配の方と話をするときには訛りが強くてわからなかったりすることが多々あります。
「んだんだ」みたいに言うこともありますからね、意味は「そうだそうだ」ということでしょう。

娘が帰宅すると早速巾着に自分の宝物を次々と入れていきます。
デザインもかわいらしいので気に入ったみたいです。

たくさん詰めて満足げな顔をしていました。
市川紙店 宮城県塩釜市本町2-15